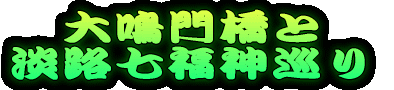
2007年5月31日、我がお袋さんが喜寿となりました。
と言うことで、そのお祝いとして
今は亡き親父が最後に手がけた現場である大鳴門橋を見せに行ってまいりました。
以下は、その旅行記であります。
PART 1
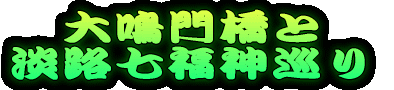
2007年5月31日、我がお袋さんが喜寿となりました。
と言うことで、そのお祝いとして
今は亡き親父が最後に手がけた現場である大鳴門橋を見せに行ってまいりました。
以下は、その旅行記であります。
PART 1
| ★2007年5月31日 ずいぶん前から、喜寿の誕生日にあわせて大鳴門橋に連れて行こうと計画をしていたのですが、いざ具体的に宿やルートの詳細を決める段になって、肝心の名神高速道路が終日工事を行う時期に合致していることに気がつきました。 高速道路の公式ホームページによると、通常の1時間以上時間がかかるということで、大変心配をしたのですが、他に早くいけるルートはなく、不安を感じながら、朝5:45分に我が家を出発しました。 小雨が降る中、前日まで残業続きの身にとっては、眠気との戦いとなるロングドライブの幕開けです。  ルートは、名神→山陽→中国→鳴門と、有料道路を乗り継いでいくものですが、やはり名神高速道路の渋滞は予測どおりでした。完全に車の動きが10分以上止まってしまう事が何回かあって、こりゃ、予定どおりポイントを回ることは無理かなぁ、と考えながら走っておりました。 しかし、途中、養老SA、泰荘PAで休憩をとり名神を抜けた頃には、流石に平日と言うこともあって、快適に車を飛ばすことができ、明石大橋を渡って、最初のポイント地点である淡路SAには、予定どおりの11時ちょい過ぎに到着することができました。 左の写真は淡路SAにある観覧車です。ここは、明石大橋を渡ってすぐのところにあり、ハイウェイオアシスを併設しています。時間がないので、ハイウェイオアシスの方はまわりませんでしたが、この観覧車の向こうは、明石大橋で、そりゃ見事な景観でございましたよ。このころには、雨は降っておらず、太陽が照りだしておりました。 淡路島に車で来た人が最初によるポイントということで、色々な淡路島観光のパンフレットなんかが、置いてあります。それらゲットして、次のポイントへ移動しました。 |
||
 淡路SAエリアを降りてすぐのところにある「淡路花舞台」。ここは、200年に開催された淡路花博のメイン会場だったところ。実に広大で敷地で花舞台そのものの入場は無料。太っ腹だねぇ。維持費が相当掛かっているだろうにね。 しかし、あまりに広大すぎて、地下の駐車場に車をいれたら、何処へ上がっていけばよいのかがさっぱりわからない。地上へあがっても、傾斜地に作られた建物は、今自分のいるところが1階なのか2階なのかわからなくなってしまいました。 見所は沢山あるのですが、我々の目的は食事。「グリル淡路夢工房」なるお店にて、淡路牛焼き肉丼と、こだわり穴子卵とじ丼をたのみました。 結局見学の方は、レストランやショップのある建物の周辺と展望テラスへ上がったのみ。本当は、もっと時間をかけて歩き回りたかったですね。右の写真は「百段苑」と呼ばれている斜面に作られた花壇です。下から見上げた写真は、ガイドブックには絶対ないよね。上まで昇る時間がなかったもんで。。。デザインは、あの安藤忠雄氏とか。 |
||
 さて、ここからが淡路七福神巡りの始まりです。 今回ほど、新しい車のナビゲーションシステムの有難みを感じたことはありませんでした。勿論、事前にポイントはすべてメモリーに記憶させ、その指示どおりに車を走らせたのですが、一箇所だけ、ナビにはない新しい道路が眼前に拡がり、勘で走ったときもありました。しかし、このような小さな寺を、ロードマップ見ながら走っていては、時間がかかって仕方がないところでした。文明の利器に感謝!といったところです。 淡路七福神巡りは、いつごろから観光化されたかよく知りません。何でも、島の形が七福神の宝船に見立てられ、全島に広く、この七福神巡りのポイントが設定されています。まぁ、淡路島は、イザナギ、イザナミが最初に創った島ですからね。 しあわせを集める寶印帳のシステムは2種類ありますが、私が選んだのは、あらかじめ七福神の絵とお寺の文字(といっても印刷でなく直筆)が入った帳面に各寺ごとに日付印を押してもらうものを選びました。帳面代+7つの寺の寶印代=700+2100=2800円というもの。 これは、淡路七福神専用の寶印帳ということです。 まず、最初は、「八浄寺(はちじょうじ)」。ここは、大黒天が祀られています。 この七福神巡りは、どこの寺からスタートしても良く、最初の寺で寶印帳を購入してまわりましょうという、ガイドブックに従って、ここで奉納金を納めました。 今から思うと、この寺が一番キレイで、大きかったように思います。お寺によってかなり施設的にも待遇的にも異なるところが、また、趣がありました。 |
||
 お次は「法生寺(ほうしょうじ)」。ここは、寿老人が祀られています。里にある本当に小さな寺で、ナビがなければ、うまくたどり着けなかったかもしれません。小さな寺なのですが、右のような不思議な橋があって、係のおばちゃん(売店みたいなところはしっかりあって、お茶の接待を受けた)が渡ると長生きするとかいわれて、お袋さんの記念写真を撮ったモノです。 お次は「法生寺(ほうしょうじ)」。ここは、寿老人が祀られています。里にある本当に小さな寺で、ナビがなければ、うまくたどり着けなかったかもしれません。小さな寺なのですが、右のような不思議な橋があって、係のおばちゃん(売店みたいなところはしっかりあって、お茶の接待を受けた)が渡ると長生きするとかいわれて、お袋さんの記念写真を撮ったモノです。そうそう寺の入口の農家で玉ねぎを売っていて、それを購入しました。淡路島は玉ねぎが名産なんですね。「花舞台」で食べた料理にも使われていましたが、滅茶苦茶に甘い玉ねぎでした。 |
||
 「覚住寺(かくじゅうじ)」です。ここは毘沙門天が祀られています。 「覚住寺(かくじゅうじ)」です。ここは毘沙門天が祀られています。ここも小さな山里のお寺でして、隣にある氏神様の方がよほどりっぱでした。 その神社を掃除している地元の人に、「七福神は隣だよぉー。」と、声をかけられました。 寺の前は、一面の玉ねぎ畑。なんかのんびりしていて良いですねぇ。 |
||
 「万福寺(まんぷくじ)」です。ここは恵比酒太神が祀られています。ふつう、恵比寿様って、この恵比寿と書きますよね。なぜか、ここは、恵比酒太神って書くんだね。 「万福寺(まんぷくじ)」です。ここは恵比酒太神が祀られています。ふつう、恵比寿様って、この恵比寿と書きますよね。なぜか、ここは、恵比酒太神って書くんだね。この寺は、街の中に込み入ったところにあって、駐車場も一番狭かった印象があります。寺のそのものは、それなりのものですけれど。 今までの寺もそうですが、寺としてのご本尊の他に七福神を祀ってあるわけで、この寺にも立派な木彫りの恵比酒太神がありました。写真にもとりましたが、今一、ピンぼけだったので掲載はできませんが。 また、外にも、立派な像がありました。 |
||
 この日最後の寺は、「護国寺(ごこくじ)」。ここは、布袋尊が祀られています。 寺そのものは、最近再建されたようで、左の写真のように立派な山門があり、中には仁王さんもいらっしゃいました。 ちょっとした庭があり、その昔、徳島藩の久米姫というお姫様が読んだ句も掲示してありました。  そうそう寺の中に喫茶室があったのも印象的。でも、本堂の前に喫茶店の看板(ほら、よくあるでしょ、ワルツ珈琲とか、キー珈琲ってやつ)は、やめてほしいなぁ。 それから瓦の布袋様がいらっしゃいました。他の寺院でも時々みかけます。 いぶし瓦も、淡路の名産とのことです。 |
||
 |
||
 かなり順調にスケジュールをこなし、この大鳴門橋を一望できる「道の駅うずしお」にたどり着いたのは、午後4時30分頃でした。 かなり順調にスケジュールをこなし、この大鳴門橋を一望できる「道の駅うずしお」にたどり着いたのは、午後4時30分頃でした。時間も時間だけに、訪れている観光客も5、6人でちょっと閑散とした感じ。 左の写真は、私が小学生の頃から、親父が愛用してたプロ使用の三脚(かなりゴッツイ)を使って、記念写真用に作られたスペースで撮りました。カメラは、親父愛用のアサヒペンタックスSPってわけではありませんが。 我が親父は、定年退職後、この大鳴門橋の淡路ルート側JVの安全管理者として3年勤めていました。我が家には、この橋がつながる寸前の写真が何枚か有ります。 吊り橋は、人間が造る構造物の中で、最も美しいものの一つだと言います。構造的に、黄金比になるようですね。間近に見る大鳴門橋は美しくも力強いものでした。 明日は、この大鳴門橋を渡って、徳島に渡ることになります。 |
||
| この日の宿は、喜寿のお祝いと言うことで大奮発して予約しました。 宿の名前は、観光旅館「うめ丸」。 観光地ですから、旅館はいっぱいありますが、インターネットで一所懸命しらべて、部屋から大鳴門橋が一望できること。そして、夕食を個室でゆっくり食べること。ができる、この宿にきめました。 たのんだコースは、別館宿泊での「鯛と伊勢エビ」コース。いやー、大名にでもなった気分でしたよ。 ものすんごい広い部屋から、大鳴門橋を見ると、こんな感じ。(勿論、望遠撮影ですよ) |
||
 |
||
| インターネットで予約したのですが、その際に、今回の旅行の趣旨を書き送っておいたところ、まず、宿についたとたん、そのネットで相手をしてくれたお姉さんからごあいさつ。 で、夕食の箸の袋には「寿」の文字。料理を運んでくるお姉さん方1人1人から、おめでとうございますと声をかけられ、オフクロはご満悦でした。 で、肝心の料理なのですが、これはもう何もいうことはありません。大満足、食べきれないほどのご馳走がならびました。(でも食べたけど) 写真も撮ったのですが、うまくとれなかったので、この日のメニューを書いておきます。 |
||
◆活造り「鯛と伊勢海老」 ・付き出し ・酢の物 ・鯛の活造り (喜寿なので通常より大きいです!とは仲居さんのお言葉) ・伊勢海老とあわびの活造り ・鯛とサザエの宝楽焼き ・有頭海老のてんぷら ・季節の一品 (1人用の鍋があったので、それのことかな) ・おしのぎ (「おしのぎ」とは、口直しの意味とかで、この日は、鯛飯) ・鯛のあら煮 ・吸い物 (海老の頭でダシをとった味噌汁でした) ・御飯 ・香の物 ・フルーツ (メロンとシャーベット) それから、このメニューにはありませんが、鯛のカルパッチョ風のものもでました。 あと、ここは「うずしお温泉」の中にあり、弱アルカリ性の泉質で、美人の湯としても人気をはくしているとか。 ぬるっとした感じの肌触りで、とても気持ちがよい温泉でした。 なんせ、平日なので、この日も入ったときも、次の日の朝風呂も、風呂の中では誰にも会わず、デカイ湯船に悠々と入ることができました。 |