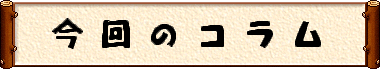
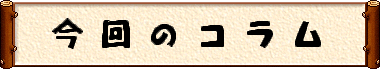
学生時代からやりたいことばかりで、アルバイトをする暇がありませんでした。このため、もっぱら、新聞、雑誌の投稿や、テレビ、ラジオのモニターをして、小遣い銭を稼いでました。
しかし、投稿した文章は、活字になる前に編集者の校正が入ります。様々な文献を引っ張り、何日も悩んだ末絞り出したフレーズが、あっさり、ありきたりの表現に書き換えられることも、しばしばありました。
そんなときは、「あ〜、この編集者は、こういう表現方法を知らないんだな。」と毒づいたものです。
そもそも、今までのメディアは、採用されなければ、人の目に付きません。ま、自費出版という手もありますが…。
しかし、インターネットの時代になり、ちっぽけな個人から、世界に向かって、簡単に、思いを発信できる時代になりました。これは、とんでもなく、すごいことだと思います。
ご感想などお待ちしております。
![]()
色々なことがあった2025年でした
勿論、2月にお袋さんが亡くなったとは、言うまでもなく私にとっては大きな出来事でしたが、その後次々と家電が壊れたことも大きな出来事でありました。
まず、地デジに変わった時に渋々買い換えたテレビが映らなくなりました。続けて、10年以上大切に使ってきた石油ファンヒーターが灯油漏れを起こし、スマホが調子悪くなり、鰹節削り機が分解し、座敷の照明の枠がバラバラになり、そして電子レンジが機能しなくなり、オマケに騙し騙し使ってきたエレクトーンまでも壊れました。まぁすべて寿命だったのでしょう。ここまで色々壊れてしまうなら、え〜いついでだと、以前よりの懸案事項であった襖や障子も張り替えました。
お袋さんの死去に伴い私も年賀状の代わりに欠礼のハガキを送付しました。また、これは30年以上前に亡くなったオヤジの時と同様、お袋さんが出していた年賀状も数年前から宛名と住所は私が打ち出していましたので、わずかではありますが、そちらにも出させていただきました。
一方、2025年も各界の有名人が何人もお亡くなりましたが、例年のごとく私自身も欠礼のハガキを何通か受け取りました。友人知人の親が亡くなったとのハガキが多いのですが、ご本人が亡くなったとのハガキも何通が頂きました。その中に今でも鮮明に思い出が残る方が2人亡くなりました。
一人は小学3年生の時の担任だったT先生です。奥さまから欠礼のハガキを受け取りました。実はT先生は私を無類の落語ファンにしてしまった方なのであります。授業中の雑談の中で「時そば」を話されたことがあり、それを家に帰ってから家族の前で話をしました。ただ、みんなが笑ったので笑ったけど、私には何が面白いのかわからなかったようです。それで、親に解説?してもらうと同時に落語というモノだよと教えてもらいました。以来、テレビ等で放送されるとチャンネルを合わせ、噺の全集みたいな本も沢山読みました。というわけで大好きになったわけですが、学生時代は東海ラジオの公開録音で放送されていた「なごやか寄席」に毎月録音会場に脚を運んでいました。
たまたま、私の所属していたサークルの隣の部室が落研で、会場でよく落研部員に会いました。その頃は、知っている落語の数は落研部員よりも多いと自負しておりましたよ。私を落語好きにして下さった恩人?のT先生が亡くなったことで、小学校の先生に出す年賀状は一通のみとなってしまいました。
もう一人は、私が他部局に出向していた三年間、仕事上もアフターファイブも大変お世話になった一回り年上のO先輩であります。この方も奥さまから欠礼のハガキを受け取りました。
Oさんは、土木上の技術は勿論、映画等の造詣も深く、仕事終わりには週に3回くらい?大曽根で呑んでいました。常連にならない限り三杯以上は呑ませないという冷凍焼酎なんてモノを教えてくれたのも彼でした。
色々な話をしましたが、話よりも1番覚えているのは、雪が足首くらいまで積もっている日に呑みに行ったと時のことです。
「こけるなよぉ」と言われているそばから私がズテッと転びました。「ほら気をつけろよ。」と言ったOさんが今度はズテッ!こりゃ危ないぞと言うことで肩を組んで歩き出したら、今度は二人同時にズテッと尻餅!馴染みの飲み屋さんについた頃には二人ともお尻が雪まみれ。店の人に笑われましたっけ。
それ以降も時々は会って呑んでいましたけど、Oさんが退職するとなかなか会うこととが出来なくなりました。昨年の年賀状には、また呑みに行きたいねぇなんて書いてあったのですけどね。
人が亡くなると言うことはホントに寂しいものです。
でも私が生きている限り、ある時代を共に生き、共に笑い共に語り合い、お世話になった方々のことを私は決して忘れはしませんからね。